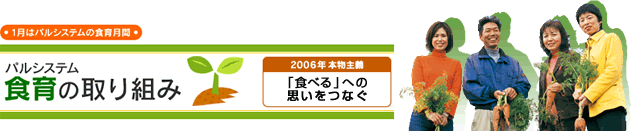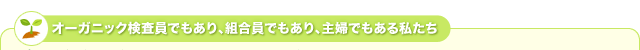|
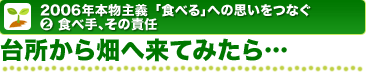

「農薬を減らす意識と努力にはすばらしいものがあります」。
口を揃えるのは、水野さん、浅野さん、太田さん。
昨年8月、公開確認会の監査人講習会「フィールドワーク編」の折、講師として産直産地・佐原農産物供給センターを訪ね、感嘆したと言います。ふだんはオーガニック検査員として、有機認証のために全国各地の畑を見る機会が多い3人。ともにパルシステムの組合員でもあります。
「講習会以来、カタログでの注文数が増えちゃって」と笑いながら、同じ組合員に対しては、「食卓や台所の都合だけでものごとを考えていませんか?」とチクリ。
「たとえば人参の袋のなかに、太いのがあったり細いのがあったりすると、『使いにくくて不便だわ』と思う人もいる。でも、畑で見れば、形もサイズも決して同じじゃない。農産物ってなかなか人間の思うようにはならないものだということが実感できますよ」(浅野さん)。

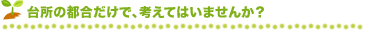

「台所」と「畑」――それぞれの事情を知る者同士が、同じ土俵で腹を割って話し合い、もっと理解しあえたら――そうした問題意識から生まれたのが、パルシステム独自の認証制度「公開確認会」です。
組合員が産地に赴き、生産者と直接顔を合わせて生産方法やプロセスを確認しあう。これまでのべ5000人以上の組合員が参加した公開確認会には、商品が約束した基準通りに作られているかどうかをチェックすると同時に、食べる側が生産現場の実態や生産者の考え方を知り、その信念や喜び、苦労に共感するという目的も込められています。
「与えられるばかりの情報が多く、消費者は考えることをやめてしまっているのでは? 畑で土に触れ、作物の育ちを五感で受け止めたら、次は現実の問題や解決方法を組合員自身が、自分の問題として考えていく。公開確認会のシステムに、そんな可能性を期待したいですね」(浅野さん)。

|