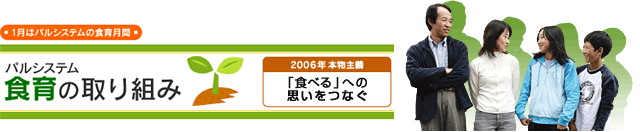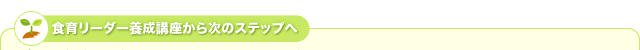|
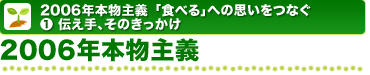

何かに感動したとき、真っ先に「伝えたい」と思う相手はだれですか?
逆に信頼するだれかが「素敵なことがあったのよ」と語りかけてきたら、「何々?」と耳を傾けたくなりませんか?
人がいきいきとくらしていく上で、「思いを共感できる相手」の存在ほど貴重なものはありません。
「『食べる』を真ん中に」という価値観を大事にしてきたパルシステム。
食べる、つくる、届ける…立場はさまざまでも、「これ、おいしいよね!」「しあわせってこういうことだよね」と共感できる相手がここにはいます。
おいしいもの、心地よいことを共に探す仲間がここにはいます。
この楽しさ、頼もしさこそが、パルシステムの「本物主義」です。
この「思い」に共感し、伝え手として食育に関わる食育リーダーを紹介します。

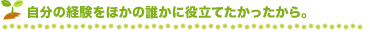

「生協の商品には助けられました」と武村奈津江さん。息子の拓哉くんが食物アレルギーで、いまも給食の献立を見て、似たようなものになるようにお弁当を作っています。「始めのころは自分だけみんなと違うのが恥ずかしかったけど、いまは慣れた」と拓哉くん。「食事制限は大変だけど、油や砂糖を使わない食事というのは、じつはからだのためによい、ということを実感している」と奈津江さんは言います。
そんな自らの経験を、ほかの誰かに役立てたい、と参加したのが、神奈川ゆめコープが実践する「食育リーダー養成講座」でした。

|