
杉山農場の有機農法について
説明する杉山修一氏 |
パルシステムでは、食の安全の確保と、環境保全型農業の推進に向け、産地での栽培や生産履歴を生協組合員と生産者がともに公開の場で確認しあう「公開確認会」を1999年より行っています。
これまでの8年間で、海外を含め77カ所の産地をのべ約6,100名の生協組合員が訪れました。
■環境保全型農業を実践する杉山農場を視察
7月24日には、2008年度3回目となる公開確認会を、パルシステムのふーど米(*1)の産地「日本の稲作を守る会」(栃木県川内郡)にて行いました。
パルシステムの組合員・役職員を始め、同産地への技術指導をしているNPO民間稲作研究所メンバー、JAささかみなどの米産地の生産者など約80名が参加しました。
午前中は、「こしひかり」を有機栽培する杉山農場(栃木県塩谷町)を視察しました。杉山農場は約40haの水田で、農薬による健康被害をきっかけに環境保全型農業に転換しました。
冬でも田んぼに水を入れるふゆみず田んぼでは、水田脇にビオトープをつくり、水田生物の復活に取り組んでいます。
農場主の杉山修一さんは、「無農薬の田んぼでは、毎日が雑草との戦いです。しかし消費者や子孫の健康に責任のとれる農産物を作りたい。多様な生きものがいる田んぼで育った元気な米の、細胞が喜ぶようなおいしさを消費者にわかって欲しいという気持ちで取り組んでいます」と有機稲作への熱意を語りました。参加者からは、採算面についてなど多くの質問があがっていました。
NPO生物多様性支援センター(*2)の田崎愛知郎事務局長は、「田んぼの生きもの調査の手法を取り入れた公開確認会は、地域の環境と調和した農業こそが食の安全につながる、ということを実感できる機会です」と話されました。
■生物多様性農法の可能性を実感した公開確認会

公開確認会の様子(塩谷町公民館) |
午後からは、塩谷町公民会にて公開確認会を行いました。
パルシステムの野村和夫産直事業部長は、「2006年に画期的な法律、有機農業推進法が成立しましたが、日本で流通する有機農産物のうち国産は5分の1に過ぎない現状で、今後の実質的な拡がり期待されます。豊かな生態系のある環境での農業の意義を皆さんに理解して欲しいと思います」とのあいさつで始まりました。
続いて、「日本の稲作を守る会」の稲葉勇美子社長が「いいものを作りたいという生産者の高い志しと真面目な努力を感じて欲しいと思います」とあいさつしました。
産地プレゼンテーションでは、同会が、1994年、前年の米騒動を契機に自主食糧管理組織として発足したこと。日本の農業を有機農法を核とした環境創造型へと転換することを基本方針に掲げていることや栽培履歴の管理組織体制などが報告されました。
また1994年、有人ヘリによる農薬散布で高校生が被災した事件を契機に、2002年栃木県で農薬の空中散布の全面中止が実現したことも報告されました。
■田んぼの生きもの調査のまとめ報告と監査人所見

「日本の稲作を守る会」
稲葉勇美子社長 |
生物多様性農業支援センター副理事の岩渕成紀氏からは、前日に監査人と共に行った「田んぼの生きもの調査」のまとめ報告がありました。杉山農場の田んぼには、カエル、ユスリカ、アメンボ他43種の生きものと、ハコベ、ハルジオンなど56種の植物が見られたとのことでした。
岩渕氏は「自分だけが安全なものを食べればいいというのはエゴに過ぎません。食べ物のできる背景にも想像力を持ち、生きものの力を最大限に活かす農法で農村の景観を復元し、環境を整えてゆくことが大切です。
杉山農場は、去年まではふゆみず田んぼでしたが、トロトロ層(*3)ができすぎたため、今年は6月下旬まで水を抜くなど田んぼの様子を見ながら、きめ細やかに対応しているところが素晴らしいです」と講評を述べられました。
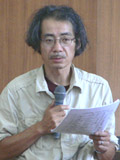
田んぼの生きもの調査
の報告をする岩渕成紀
氏 |
監査人所見では、「高度成長とともに育ち、大規模な田んぼでの効率優先の農業に変化してゆくのを見てきた世代ですが、今回、お米は豊かな生態系の産物なのだということを実感しました」「実際に田んぼに入ってみて、慣行栽培の田んぼとの泥の感触の違いを実感しました。人と自然の繋がり、生産者の緻密な努力でおいしいお米ができるのだと感じました」「ここで学び感じたことを持ち帰って多くの人に伝えたいと思います」などの感想を述べていました。
参加者全員が、生産者の米づくりへの真摯な姿勢と熱意に共感し、自給率低下や生産者の高年齢化などの農の問題への光明として、生物多様性農法の可能性を実感した公開確認会となりました。
【資料】
「日本の稲作を守る会」

民間稲作研究所代表の稲葉
光國氏 |
「日本の稲作を守る会」は、“安全でおいしい有機栽培米や無農薬栽培の生産を援助し、自給を維持すること。永続的な農業経営と農村の自然環境を守ること”を目的に、1994年に結成されました。会員農家はNPO法人民間稲作研究所(代表はNPO生物多様性農法支援センター(*2)副理事長 稲葉光國氏)の開発した環境創造型の有機稲作を導入し、米作りの技術を高めてきました。パルシステムとは2007年度から、有機米の取引が始まりました。
田植え前から、新米の予約をすることで環境保全型農業を支援する仕組み「予約登録米」の産地です。
 日本の稲作を守る会(新しいウィンドウが開きます) 日本の稲作を守る会(新しいウィンドウが開きます)
(*1)ふーどのお米
パルシステムでは、全国30の産地から年間約2万4千トンのお米をお届けしています。そのうちの約半数が、化学合成農薬や化学肥料の使用を、産地の一般的な使用量の半分以下に削減した「エコ・チャレンジ栽培米」(特別栽培米)です。 なかでも、パルシステムのトップブランド「the ふーど」のお米は、種子の段階から化学合成農薬および化学肥料を使用しないなどの基準をクリアしています。JAS法の定める「有機栽培」か、それに準ずると判断されたこだわりのお米です。
(*2)生物多様性農業支援センター
パルシステム連合会は、2004年に「田んぼの生きもの調査」を4産地で実施しました。2005年にはNPOふゆみずたんぼ(岩渕成紀代表)、NPO法人民間稲作研究所(稲葉光圀代表)、全農、(社)農村環境整備センターを中心に「田んぼの生きもの調査プロジェクト」を結成しました。同プロジェクトは、2008年5月、農に根ざした地域の伝統文化を守り、地球環境問題に取り組む人々を支援するため、NPO法人「生物多様性農業支援センター」として新たに発足しました。
(*3)トロトロ層
冬期湛水により土壌表面に形成されるトロトロとした感触の土層。通常、冬期湛水を2年継続すれば3〜5cm程度のトロトロ層が形成されます。イトミミズにより形成されるとされているが、冬期湛水だけではなく不耕起や無農薬・無化学栽培、コメヌカやクズダイズなど有機資材の投入で形成が促進されるようです。雑草種子を埋没させるので、雑草の発芽抑制の効果があるともいわれています。
(*4)生物多様性農法
生産効率を上げるための化学肥料や農薬に依存せず、微生物や昆虫、魚、カエルなど、田んぼや周辺に生息する多様な生きものの生態系を活かすことにより作物を育てる農法

杉山農場の田んぼ |

【杉山農場の田んぼの生きもの】(左から)ハグロトンボ、タイコウチ、ガムシ、イチョウウキゴケ |
<関連リンク>
 田んぼの生きものから環境創造型農業をつくる NPO法人「生物多様性農業支援センター」が設立されました(2008年5月28日ニュース) 田んぼの生きものから環境創造型農業をつくる NPO法人「生物多様性農業支援センター」が設立されました(2008年5月28日ニュース)
|
|