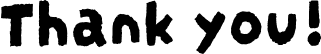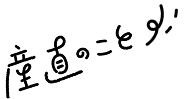
いっしょにつくる ココロはずむ物語
#いただきますのその先へ #産地へ行こう
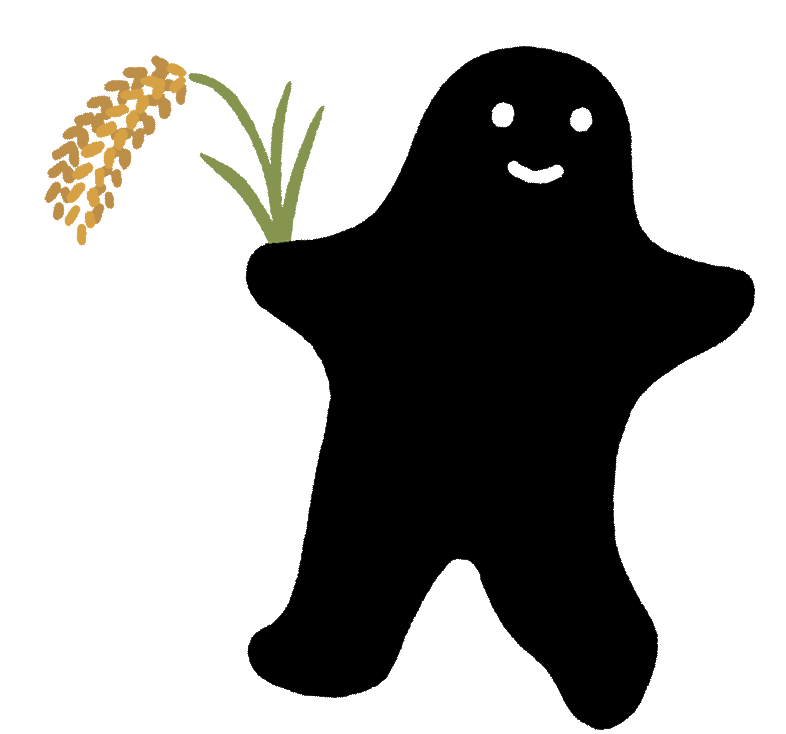
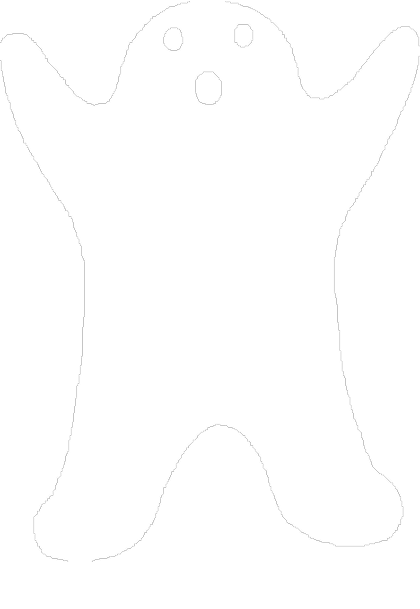
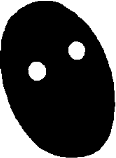
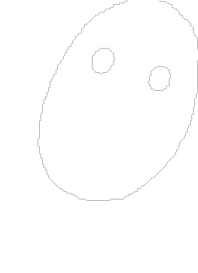


いつも食べてる
お米、肉、魚、野菜、果物。
どんな人がどんな思いで
作ってるんだろう。
「いただきます」の先にある物語に
会いに行ってみたら
食べることが、ぐっと近くなります。



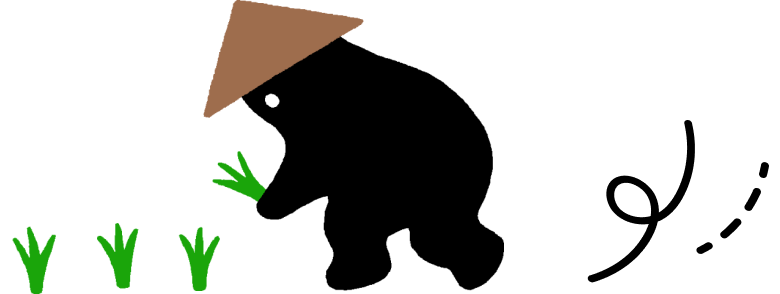
田んぼが紡ぐ
時を超えたつながり
#JA新潟かがやき(新潟県)
#お米のふるさとささかみ

新潟県阿賀野市のささかみ地区は、おいしいお米のふるさと。山の緑と田んぼの風景が広がる地域です。昔から変わらない風景の中で、今もていねいに米作りを続けています。
お米の直接取り引きがむずかしかった1970年代。しかしパルシステムは組合員に安心安全なお米を届けるため、産直提携先を探していました。そこでたどり着いたのが、米作りにこだわりを持ったささかみの人たち。何度も話し合いを重ね、まずは交流から関係を築いていったのです。
春には田んぼに足を踏み入れて苗を植え、秋には黄金色に実った稲を刈る。JA新潟かがやきのささかみ地区では今も、田植えや生きもの調査、収穫などの産地交流が、年間を通して行われています。

参加した子どもたちからは「こんなにおいしいお米は初めて!」という声も。お米がどうやって育つのかを見て感じることで、生産者への感謝や食べ物への思いが、自然と育まれていきます。
子どものころに参加した組合員が、今度は自分の子どもを連れて。そんなふうに、この取り組みは40年以上脈々と続いています。
交流を重ねるなかで、本当の意味での「顔の見える関係」が築かれていきます。ささかみとの交流は、パルシステムにとって「産直」の原点ともいえる、なくてはならないものなのです。

Watch & Learn
ちょっとフカボリ
「JA新潟かがやき(旧JAささかみ)」ってこんなところ
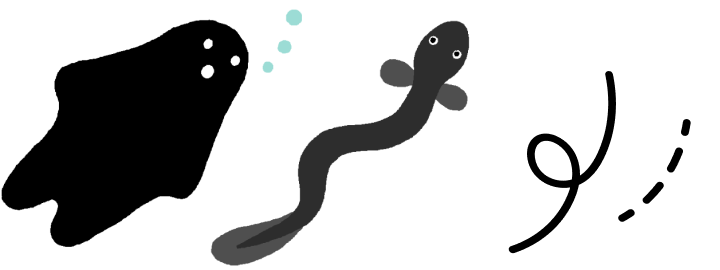
うなぎのすむ川には
発見がいっぱい!
#大隅地区養まん漁業協同組合(鹿児島県)
#うなぎに会いに行こう

温暖な気候と豊かな水に恵まれた九州・鹿児島の大隅半島。この地で育つ「大隅のうなぎ」は、パルシステムで長年愛されている産直品のひとつです。
1980年代以降、日本でとれるうなぎの稚魚である「シラスウナギ」が減っていました。2013年、ついにはうなぎが絶滅危惧種に。そこでパルシステムは、大隅地区養まん漁協とともに「大隅うなぎ資源回復協議会」を立ち上げました。
協議会で生態調査に取り組むと、うなぎの減少理由のひとつに河川環境の悪化がありました。そこで組合員や職員が、うなぎや環境のことを学ぶきっかけとして、産地ツアーをスタート。

訪れた子どもたちは川に入り、生産者や専門家の先生から、うなぎのくらしや、隠れ場所について教えてもらいます。うなぎをはじめ生きものと触れ合うことは、環境への関心や気づきが生まれるきっかけにも。
うなぎを守ることで、未来の自然環境を豊かにすることにもつながります。パルシステムが生態調査の一環で行っている、うなぎのすみかを作る取り組みは、今では全国に広がっています。
自然環境と日本の食文化を守っていくこと。子どもたちに伝えることで、その記憶は大人になっても心に残り続け、次の世代へとつなぐ一歩になっていきます。

Watch & Learn
ちょっとフカボリ
うなぎと生きるみち。「大隅うなぎ資源回復協議会」
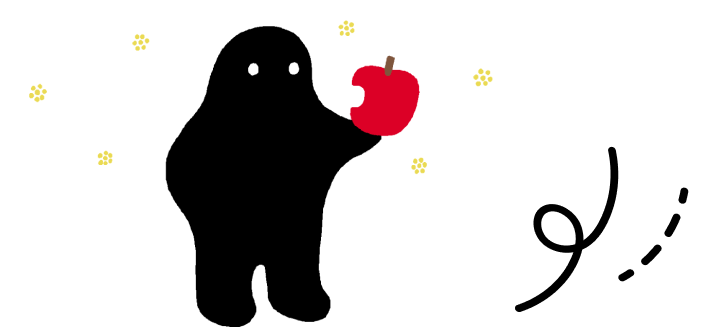
りんご畑から始まる
新しい絆
#アップルファームさみず(長野県)
#「援農」がつなぐ未来

標高が高く自然に囲まれた長野県飯綱町にある、アップルファームさみず。昼夜の寒暖差が大きく、おいしいりんごが育つ好条件がそろった「りんごの里」です。
りんご栽培の作業はひとつひとつ手作業で行うため、時間も人手も必要です。パルシステムでは、2024年から援農ボランティアのツアーを始めました。年に2回、5月には未熟な花や実を取り除く作業、11月には熟した実を収穫します。
作業は、実際に商品になるりんごの畑で行います。最初はおそるおそるだった組合員も、少しずつ慣れ、最終的に予定の2倍の量の収穫ができたことも。

葉のカサカサと揺れる音、虫の羽の音。夢中で作業をしていると、聞こえてくるいろんな音。自然の中にいると、ふだんなかなか意識することのない感覚に、そっと気づかされます。
また、「一番上のりんごって、こんなにとるのが大変なんだ」と産地の苦労を知る機会でもあります。生産者といっしょに農作業をすることは、ただ畑を訪れるよりもずっと、食べ物や産地への思いが深まります。
産地にとって一番重要で忙しい時期に足を運ぶこと。援農ツアーでは、組合員も本気の作業が求められます。産地の課題にいっしょに向き合っていくためにできることを、これからも一体となって考え続けていきます。

このストーリーはいかがでしたか?