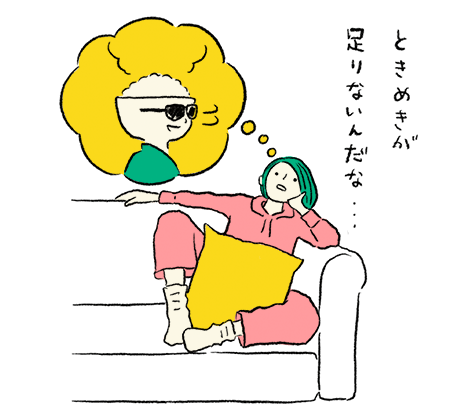ごはんづくりのNEW問答No.28

「何を作っても味がしまらず悩んでいます。私が作る料理はいつも味がぼやけています。味見をして作っていてもなんの調味料が足りないのかが分かりません。ぼやけた味のしめ方や、コクを出す調味料の使い方のコツがあったら教えてください。」(Sさん 40代)
失敗を恐れず、色々な味付けに挑戦して!

今回の回答者
食文化史研究家 魚柄仁之助さん
正解はひとつにあらず、それが料理です
おいしい味のコツを古今東西の料理の技から拾いだしてみました。
お汁粉やぜんざいにはお砂糖ばかりではなく、ちょっぴりの塩を入れなきゃ甘みやウマミは出てきません。濃厚な鰹節の出汁も塩味を加えなきゃウマミは出ません。
かけうどん、焼き鳥、ステーキなどに柑橘類のしぼり汁を数滴かけるだけで味が引き締まります。やや水っぽい鮪の赤身でも油脂を加えると大トロのようなコクが出てきます。
脂ののっていない白身魚の刺し身をオリーブ油と塩で和えればコクのあるカルパッチョになります。おでんの鍋にトマトを入れて煮るとまるで昆布出汁のようなウマミが出ます。

おいしい味は、”組み合わせの妙”でできている
これらのコツを普段のお料理に利用すればぼやけた味の解消につながるのではないでしょうか。
市販のカレールウだけでは一味足りない?カレーにはみそを少し足すことで深みのある自慢のカレーに化けるのです。
みそ汁の具がねぎしかないようなときに少量のベーコンを入れることで絶品のみそ汁に仕上げたのは天下の食通、魯山人(ろさんじん)でした。ベーコンの脂肪、塩分、アミノ酸を活かしたんですね。このようにしておいしい味は作られてきたのです。
おいしい味は組み合わせの妙で作られます。うま味調味料と呼ばれているものでもそれ単体ではあまりウマミはない。しょっぱさ、甘さ、油脂のコクなどとの組み合わせがあって初めて美味が生まれますから失敗を恐れず組み合わせてみましょ。

うまみ・甘み・酸味・塩けが詰まった幻の万能調味料「煎り酒」
江戸時代、煎り酒という調味料がありました。一升の酒に梅干し10個とかつお節を加えて、1/10量に煮詰めたものです。酒の甘み、梅の塩味と酸味、かつお節のうまみ(イノシン酸)を組み合わせた高級調味料でした。ご家庭で作るのであれば、酒100cc、みりん50cc、つぶした梅干し1個分、かつお節を計量カップにふんわり盛って50cc分、を鍋に入れて、さっと煮立ててください。本物じゃないけど、煎り酒風調味料の完成です。醤油のようにお刺身につけたり、おひたしにかけたり、幻の調味料で引き締まった美味をお試しくださいまし。
今回の回答者
食文化史研究家
魚柄仁之助(うおつか・じんのすけ)さん
1956年福岡県生まれ。食文化史研究家。食文化史の研究のなかで身につけた知恵を、自ら日々実践し続けている。著書『うおつか流 食べつくす! 一生使える台所術』(農山漁村文化協会)、『幻の麺料理 再現100品』(青弓社)『台所に敗戦はなかった―戦前・戦後をつなぐ日本食[文庫版]』(筑摩書房)など。